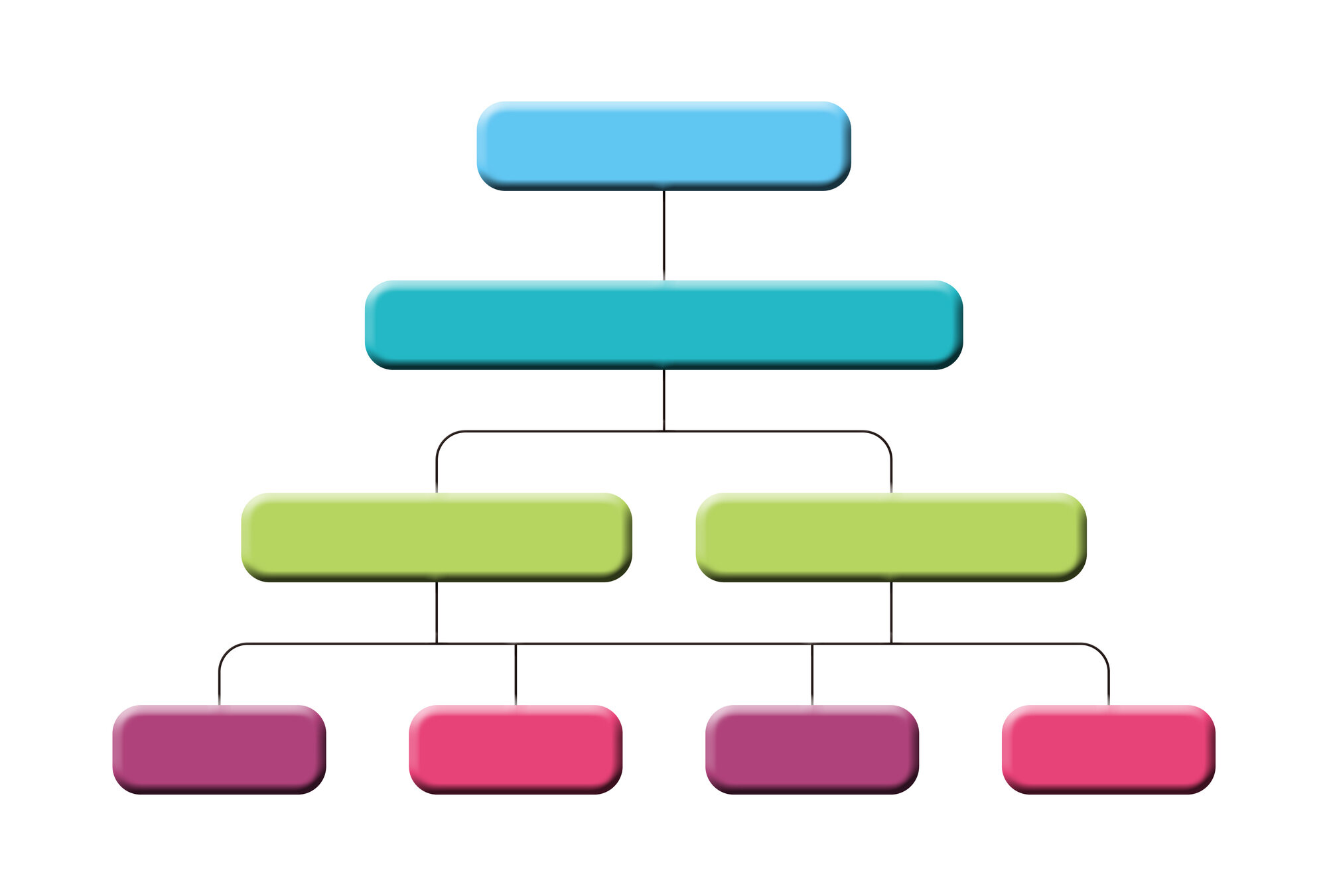本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。
- 2025/08/07公開
【第4回】「変わり続ける経営体」はどう設計されるのか、三井物産の実践から学ぶ──静かなる大改革が、日本企業に示す新しい経営モデル──

【第1回】総合商社は“経営の最前線”へ、三井物産が挑む「脱・仲介」戦略とは
【第2回】脱炭素は“リスク”ではなく“収益源”、三井物産の逆転サステナ戦略
【第3回】ゼネラリストを超えて“経営人材”へ、三井物産の人と組織の進化論
【第4回】「変わり続ける経営体」はどう設計されるのか、三井物産の実践から学ぶ
この記事を書いた人
目次
「巨大であること」は変化できない理由にならない
変革を支える“三位一体”の構造デザイン
「変わり続ける力」こそが、次代の競争優位になる
「実行される戦略」は“人”から始まる
三井物産から学べる、経営の5つの原則
この分析にMBAの学びはどう活きるか?
「巨大であること」は変化できない理由にならない
総合商社という存在は、ともすれば「変化に鈍い」「古い日本型組織」と見られがちです。
数万人の社員、重厚な業務構造、意思決定の多段階性。これらは従来であれば、こうした特徴は変革を阻む要因と考えられてきました。
しかし三井物産は、むしろ「巨大だからこそ、変われる構造」を設計し、自らを“持続的変化体”として機能させてきました。
・戦略を描き切る力
・組織を変え抜く力
・人を動かし続ける力
この三つが有機的に連動しているからこそ、三井物産は過去を否定せず、未来に適応する企業であり続けられるのです。
変革を支える“三位一体”の構造デザイン
三井物産の変革は、“個別の施策の連打”ではありません。 むしろ、経営構造を貫く“設計思想”が全体を一貫させていることが特徴です。
| 領域 | 経営レイヤーごとの進化のポイント |
|---|---|
| 戦略 | 取引型から“事業経営型”へ転換し、 長期視点での収益創出へシフト(第1回) |
| 事業構造 | カーボンニュートラル・ヘルスケア等、 社会課題と収益をつなぐモデル設計(第2回) |
| 組織・人材 | ゼネラリスト依存を脱し、 “経営する人材”を起点に組織を組み直す(第3回) |
このように、単一領域の改革ではなく、「経営の仕組みそのものを動かす」姿勢が成功の鍵となっています。
「変わり続ける力」こそが、次代の競争優位になる
企業にとって最も価値ある資質とは、“何をしているか”ではなく、“どう変化できるか”にあります。
三井物産は、「○○業界の会社」ではなく、「変化を続けられる構造そのもの」としての経営体を目指しています。
これは、MBAで言う「ダイナミック・ケイパビリティ(変化対応能力)」── すなわち、市場の変化に応じて自らのリソース構造・戦略を再構築できる能力に他なりません
「実行される戦略」は“人”から始まる
三井物産の事例から学べる最大の教訓は、「戦略=紙ではなく、組織に染み込ませてこそ意味を持つ」ということです。
・事業戦略は、経営に挑む人材がいなければ絵に描いた餅
・ESG戦略も、日々の意思決定に埋め込まれなければ意味がない
・組織再設計は、“制度設計”ではなく“行動と文化の設計”でこそ真価を発揮する
つまり、変革とは“構造の話”であると同時に“人の話”でもあるのです。
三井物産から学べる、経営の5つの原則
① 戦略とは、やめることを決めること
テレビやPC、石炭事業の縮小など、“撤退の選択”も戦略の一部。
② 組織は、構造よりも“動き方”がすべて
機能別か事業別かではなく、ミッションごとの柔軟な連動がカギ。
③ ESGはコストではなく、構造的な事業機会
脱炭素、水素、再生可能エネを“稼ぐ力”に変える設計力。
④ 人は“設計された仕組み”で育ち、“意志ある役割”で動く
キャリアを自らデザインし、経営に参加する構造づくりが進む。
⑤ 変化を習慣にできる企業が、最終的に勝つ
「変わった企業」ではなく、「変わり続けられる企業」になる。
この変革にMBAの学びはどう活きるか?
三井物産のこの変革を深く理解するには、経営の複数レイヤーにまたがる横断的な視座が必要です。
| MBA分野 | 対応する内容 |
|---|---|
| 経営戦略 | 事業ポートフォリオ/ESG事業の戦略化 |
| 組織設計 | 役割ベース構造/プロジェクト型組織への転換 |
| 人材マネジメント | リーダーシップ育成/行動評価制度の実装 |
| コーポレートガバナンス | 持株会社化による統治構造の高度化 |
これらを統合的に理解・応用できるようになることが、MBA的な“経営を見る力”の実践的価値です。
終わりに──“静かなる改革”にこそ、変革の本質がある
三井物産の変革は、決して派手ではありません。
新しいビジネスモデルを掲げたり、創業ストーリーで注目を集めるスタートアップでもありません。
しかし、彼らが実現しているのは、構造・人・文化をすべて設計し直すことで、“変化する力”を構造・文化・人材に根づかせる経営の実践”です。
この静かなる大改革は、すべての企業にとって普遍的な問いを投げかけています。
あなたの組織は、変わり続けられる構造を備えていますか?
次回は、また別の業界・企業の事例を取り上げていく予定です。あなた自身の現場と重ねながら、引き続き一緒に考えていきましょう。
アビタスでは、国際認証を取得している「マサチューセッツ州立大学(UMass)MBAプログラム」を提供
国際資格の専門校であるアビタス(東京)が提供しているプログラムで、日本の自宅からオンラインで米国MBA学位を取得できます。
日本語で実施する基礎課程と英語で行うディスカッション主体の上級課程の2段階でカリキュラムが組まれているため、英語力の向上も見込めます。
世界でわずか5%のビジネススクールにしか与えられていないAACSB国際認証を受けており、高い教育品質が保証されているプログラムです。
自宅にいながら学位が取得できるため、仕事や家事と両立できる点も強みです。
アビタスでは無料のオンライン説明会と体験講義を実施しています。興味のある人はお気軽にお問い合わせください。
 UMass MBA
UMass MBA