本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。
- 2025/10/24公開
- 2025/10/30更新
【第3回】NTTの研究開発と“IOWN構想”──巨大通信企業は「技術革新の旗手」になれるのか──
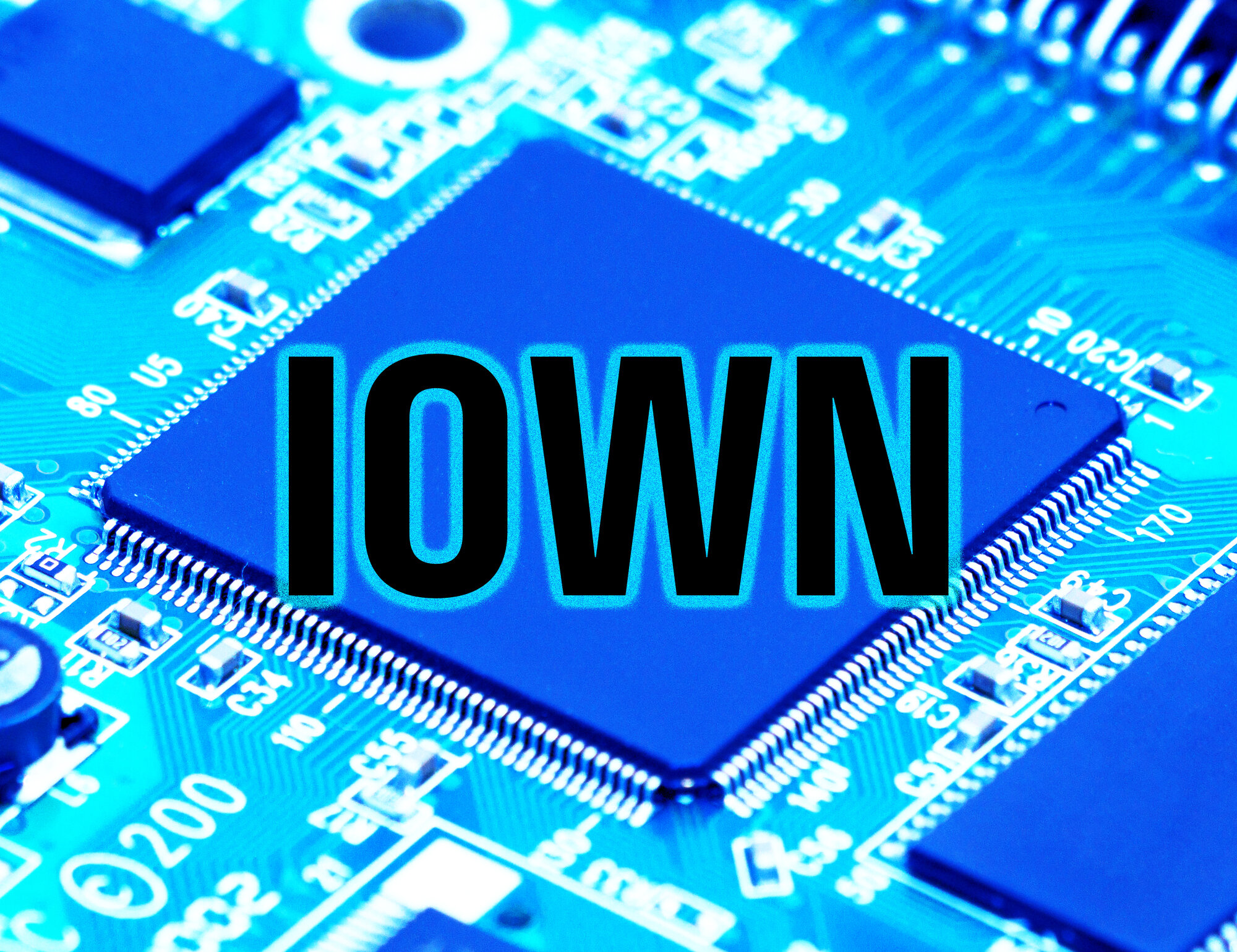
【第3回】NTTの研究開発と“IOWN構想”
この記事を書いた人
目次
世界有数の研究開発企業
IOWN構想とは何か?
なぜIOWNが必要なのか?
パートナーシップによる推進力
課題とリスク
ケースで見る実装例
MBAの学びとの接点
世界有数の研究開発企業
NTTは売上規模だけでなく、研究開発(R&D)投資額でも世界有数の存在です。
・年間R&D投資:約5,000億円(2023年度ベース)
・研究者数は6,000人以上、基礎研究から応用研究まで幅広くカバー
・研究テーマは通信インフラ、AI、量子暗号、光技術、データセンターなど
しかし課題もありました。巨額投資の割に「収益化・事業化が遅い」「海外展開で劣後する」という批判が繰り返されてきました。
IOWN構想とは何か?
2019年、NTTが発表した「IOWN構想(Innovative Optical and Wireless Network)」は、その集大成とも言える挑戦です。
狙い
インターネットの限界を超える新しい情報通信基盤をつくる
技術的柱
①オールフォトニクス・ネットワーク(電子から光へ。消費電力を100分の1に、伝送容量を125倍に)
②デジタルツインコンピューティング(現実世界をデジタルで再現しシミュレーション)
③コグニティブ・ファウンデーション(AIによる全体最適化)
これは単なる通信の次世代化ではなく、「データ社会全体の基盤」を再設計する壮大なプロジェクトです。
なぜIOWNが必要なのか?
NTTが掲げるIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想の背景には、既存の通信インフラが直面する3つの“限界”があります。
インターネットの物理的限界
現在のネットワークは電子ベースで動作しています。しかし世界のデータ通信量は2030年には2020年比で10倍以上に達すると予測され、既存技術では消費電力や遅延が限界に近づいています。すでにデータセンターの電力消費は一国の電力使用量に匹敵する水準に達しつつあり、光ベースの新インフラなしには持続的な成長が難しい状況です。
社会課題の高度化
気候変動対策に必要な気象シミュレーション、都市の交通混雑を解消する自動運転システム、遺伝子解析やリモート医療など、膨大なデータ処理を瞬時に行う社会的ニーズが高まっています。既存ネットワークでは処理速度とエネルギー効率が追いつかず、次世代技術の導入が必須になっています。
国際競争の激化
米国のGAFA、中国のBATがクラウドやプラットフォームを支配する中、日本の通信事業者が「単なる回線提供者」に留まれば、付加価値を奪われ続けるリスクがあります。そこでNTTは、インフラレベルで「日本発の標準」を打ち立て、国際競争力を確保しようとしているのです。例えば、IOWN構想は米Intel、Sony、NECなどとも連携し、国際標準化団体(IOWN Global Forum)を通じて世界基準化を進めています。
つまりIOWNは、「通信会社の延長線」ではなく、エネルギー効率・処理速度・標準化の観点から、NTTを『社会基盤提供者』へと再定義する取り組みに他なりません。
費用は留学の1/10
AACSB認証の高品質な米国MBAをオンラインで取得
まずは無料の説明会にご参加ください。
パートナーシップによる推進力
NTTは単独でなく、グローバル連携によってIOWNを進めています。
・IOWN Global Forum(2019年設立)
・ソニー、インテル、米国シスコ、マイクロソフトなど世界的企業が参加
・2024年時点で加盟企業は100社以上に拡大
・実証実験:医療画像のリアルタイム共有、都市交通シミュレーション、5G/6G連携などが進行中
「標準化」を握ることが、NTTの真の競争優位につながる狙いです。
課題とリスク
革新的なビジョンであるIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)ですが、その実現にはいくつもの高いハードルが存在します。
投資規模の巨大さ
光技術を基盤にした新インフラを世界規模で展開するには、10年以上のスパンで数兆円規模の投資が不可避です。NTT自身の年間研究開発費は約5,000億円に達しますが、IOWNをフルスケールで商用化するにはその数倍の資金が必要になると見込まれています。単独では賄えず、パートナー企業や政府支援との連携が前提条件になります。
規制との摩擦
NTTは「国策企業」としての側面を持ち、株式の約3分の1は政府が保有しています。そのため海外M&Aや資金調達の自由度には制約があり、米国や欧州の競合がスピード感を持って動くのに比べ、身動きが取りづらい現実があります。例えば、海外通信事業者との提携に際しても「安全保障上のリスク」が常に議論され、戦略決定のスピードが落ちやすいのです。
事業化の不透明さ
IOWNが提供する「超低遅延・低消費電力」の通信技術は革新的ですが、それをどう収益化するかは未確定です。現状ではB2B向け(自動運転、スマートシティ、医療データ伝送など)が中心ですが、消費者向けサービス(次世代モバイルやXR体験)にどこまで拡張できるかは未知数です。技術のポテンシャルは大きくても、「誰が顧客となり、どの市場で収益を生むのか」という問いに明確な答えはまだ出ていません。
MBA的に言えば、これはまさに「技術開発と事業戦略のアラインメント」が試される局面です。つまり、技術シーズを社会的ニーズと結びつけ、持続可能な収益モデルにどう転換できるかが、NTTの未来を左右するのです。
ケースで見る実装例
すでに一部ではIOWN技術が実証されています。
スポーツ観戦の超低遅延中継
ラグビー・サッカーの国際試合で、従来比1/200秒の遅延で映像伝送。
医療遠隔診断
手術映像をリアルタイムで複数拠点に共有し、海外専門医と連携。
都市OS
自治体との連携による都市交通シミュレーション、エネルギー消費最適化。
「社会課題解決に直結する技術」である点が、従来の通信インフラ事業との大きな違いです。
MBAの学びとの接点
| MBAの論点 | NTT事例の示唆 |
|---|---|
| イノベーション戦略 | 巨大R&D投資を社会価値に転換する仕組み設計 |
| 国際経営 | 技術標準化を通じた国際競争戦略 |
| サステナビリティ経営 | 消費電力1/100を目指す技術革新はESGの核心 |
| 経営戦略論 | 「通信会社から社会基盤企業へ」の事業定義の再構築 |
次回予告
第4回では、これまでの議論を踏まえ「NTTの変革から学ぶ経営の本質」を整理します。規制産業での変革、巨大組織の再編、技術革新への挑戦を総合し、私たちが学ぶべき3つの経営視点を提示します。
次の記事はこちら
費用は留学の1/10
AACSB認証の高品質な米国MBAをオンラインで取得
まずは無料の説明会にご参加ください。
アビタスでは、国際認証を取得している「マサチューセッツ州立大学(UMass)MBAプログラム」を提供
国際資格の専門校であるアビタス(東京)が提供しているプログラムで、日本の自宅からオンラインで米国MBA学位を取得できます。
日本語で実施する基礎課程と英語で行うディスカッション主体の上級課程の2段階でカリキュラムが組まれているため、英語力の向上も見込めます。
世界でわずか5%のビジネススクールにしか与えられていないAACSB国際認証を受けており、高い教育品質が保証されているプログラムです。
自宅にいながら学位が取得できるため、仕事や家事と両立できる点も強みです。
アビタスでは無料のオンライン説明会と体験講義を実施しています。興味のある人はお気軽にお問い合わせください。
 UMass MBA
UMass MBA







