本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。
- 2025/10/23公開
- 2025/10/30更新
【第2回】NTTの組織再編は何を変えたのか?──「分割」と「統合」に揺れ動く巨大グループの戦略──
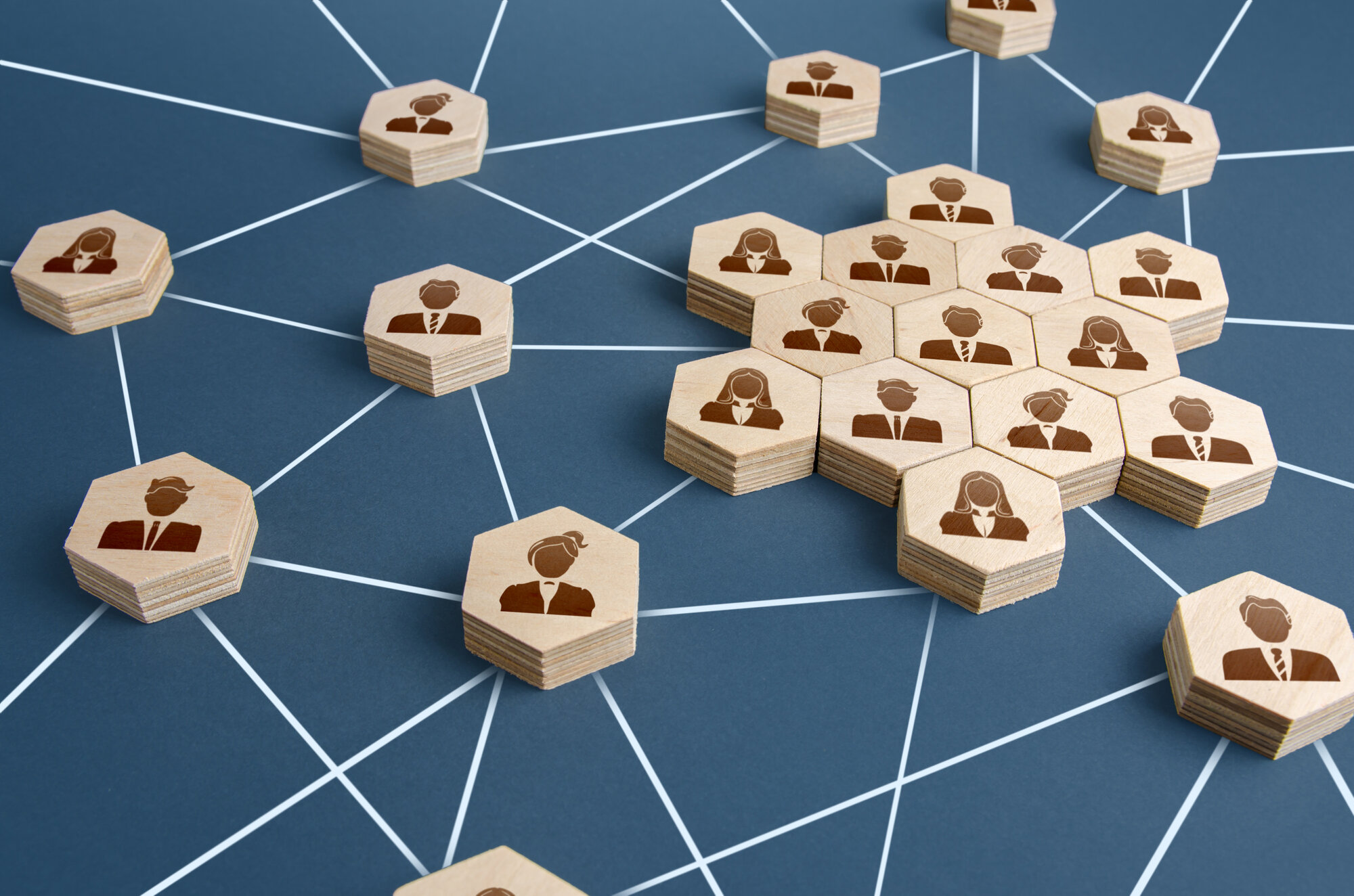
【第2回】NTTの組織再編は何を変えたのか?
この記事を書いた人
目次
1999年──持株会社化と分割の衝撃
分割がもたらしたメリットと課題
2020年──ドコモ完全子会社化の衝撃
分割と統合の“揺れ”が示すもの
ケースで見る実効性──法人向けビジネスの加速
MBAの学びとの接点
1999年──持株会社化と分割の衝撃
1999年7月、NTTは大規模な組織再編を断行しました。背景には、「独占禁止」と「競争促進」を狙う政府の意向がありました。
NTT持株会社(戦略本社)
NTT東日本・NTT西日本(固定通信事業)
NTTコミュニケーションズ(長距離・国際通信)
NTTドコモ(移動体通信)
NTTデータ(システム開発)
こうしてNTTは「巨大一社」から「持株会社の下に分かれたグループ企業群」へと生まれ変わりました。
狙いは、固定電話の独占を抑制し、公平な競争環境を整えること。しかし実態としては、グループ間の縦割りが強まり、「全社最適」から遠ざかる副作用も生みました。
分割がもたらしたメリットと課題
メリット
・各社が独自に経営判断を行い、市場変化に対応しやすくなった
・ドコモ、データといった成長分野の独立性が高まり、スピード感を確保
課題
・グループ内でサービスが重複し、調整コストが増大
・技術や顧客データの共有が進まず、シナジーが限定的
・「規制のための分割」が、グローバル競合に対して非効率を招いた
MBA的に見ると、ここでの問題は「部分最適 vs 全体最適」の典型例です。
2020年──ドコモ完全子会社化の衝撃
それから約20年後の2020年、NTTはNTTドコモを完全子会社化しました。買収総額は約4.3兆円。これは当時、日本企業のM\&Aとして史上最大規模のディールであり、国内外の市場関係者を驚かせました。
背景
携帯料金の引き下げを求める総務省の政策により、ドコモの収益性は低下傾向にありました。営業利益率は2000年代前半の20%超から、2010年代後半には10%台前半まで低下。単独上場のままでは成長戦略を描きにくくなり、親会社NTTとの一体運営が必然となったのです。
狙い
グループ内で重複していた基地局投資やシステム開発を削減し、資本効率を改善すること。そして5G・IoT・クラウドなど次世代分野では、NTTコムやNTTデータと連携し、法人向けソリューションを強化する全社最適を実現することが目的でした。
成果
子会社化後、NTTグループとして通信からクラウド、アプリケーション開発までを一気通貫で提供できる体制が整備されました。特に法人向けでは「5G+クラウド+データ活用」のセット提案が進み、NECや富士通との協業によるオープンRAN開発など、国内外での技術的な存在感も高まりつつあります。
まさに「分割」から「統合」への大転換が起きた瞬間であり、日本の通信産業にとっても歴史的な節目となりました。
費用は留学の1/10
AACSB認証の高品質な米国MBAをオンラインで取得
まずは無料の説明会にご参加ください。
分割と統合の“揺れ”が示すもの
1999年の分割と2020年の統合。この2つを比較すると、NTTの経営構造をめぐる根本的な教訓が浮かび上がります。
規制は時代とともに変わる
1999年当時は「NTTの独占抑制」が最優先課題でした。しかし2020年には、GAFAや中国勢との競争が激化し、「国際競争力の確保」が政策の焦点に移りました。同じ企業でも、求められる役割は時代の要請によって大きく変わるのです。
全社最適の視点が不可欠
分割は事業会社の自律性を高め、競争を生みましたが、その一方で研究開発や投資が分散し、シナジーを削いだ面も否めません。逆に統合は効率性を高めたものの、今度は規制当局との摩擦が強まるという新たな課題を生みました。
巨大グループの経営は“設計思想”が問われる
結局のところ重要なのは、組織図をどう変えるかではなく、「どの事業を統合し、どこを自律させるか」という全体設計の思想です。NTTの場合、研究開発は集中させつつ、地域通信事業(NTT東西)は公益性の観点で独立性を維持するなど、バランスを取った構造設計が求められています。
この「分割と統合の揺れ」は、巨大企業が時代の要請に応じて**構造そのものを柔軟に変える必要性を示す象徴的な事例だと言えるでしょう。
ケースで見る実効性──法人向けビジネスの加速
ドコモ完全子会社化後、NTTは法人市場への注力を強めました。
・5Gと光回線を組み合わせたソリューション展開
・NTTデータのシステム開発力を活用したB2Bサービス
・海外展開では、米国のデータセンター事業(NTT Global Data Centers)が拡大
これは「通信会社からソリューション企業へ」という構造転換の象徴でした。
MBAの学びとの接点
| MBAの論点 | NTT事例の示唆 |
|---|---|
| コーポレート・ガバナンス | 規制環境下でのグループガバナンスの設計 |
| 組織デザイン論 | 分割による自律性と、統合によるシナジーのバランス |
| 経営戦略論 | 全社最適のポートフォリオ設計と成長ドメインの明確化 |
| M&A戦略 | ドコモ完全子会社化という巨額M&Aの意義とリスク管理 |
NTTの20年は、「分割」と「統合」の間で最適解を探り続ける組織実験だったと言えます。
次回予告
第3回では、NTTが誇る研究開発力と「IOWN構想」に焦点を当てます。規制と巨大組織の壁を乗り越え、グローバルな技術リーダーになれるのか。その挑戦を分析します。
次の記事はこちら
費用は留学の1/10
AACSB認証の高品質な米国MBAをオンラインで取得
まずは無料の説明会にご参加ください。
アビタスでは、国際認証を取得している「マサチューセッツ州立大学(UMass)MBAプログラム」を提供
国際資格の専門校であるアビタス(東京)が提供しているプログラムで、日本の自宅からオンラインで米国MBA学位を取得できます。
日本語で実施する基礎課程と英語で行うディスカッション主体の上級課程の2段階でカリキュラムが組まれているため、英語力の向上も見込めます。
世界でわずか5%のビジネススクールにしか与えられていないAACSB国際認証を受けており、高い教育品質が保証されているプログラムです。
自宅にいながら学位が取得できるため、仕事や家事と両立できる点も強みです。
アビタスでは無料のオンライン説明会と体験講義を実施しています。興味のある人はお気軽にお問い合わせください。
 UMass MBA
UMass MBA







