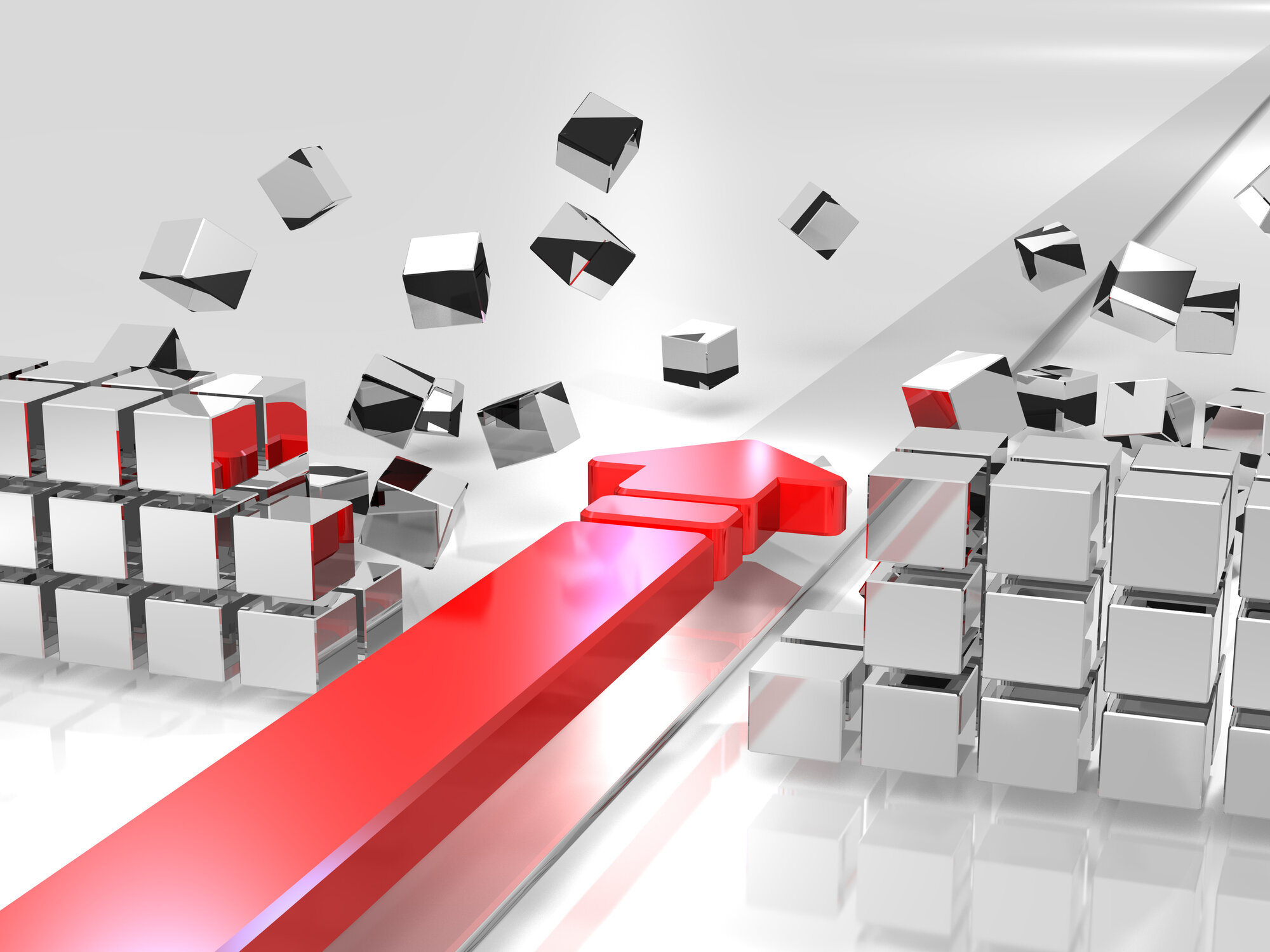本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。
- 2025/10/16公開
【第3回】再建後のJALに待ち受けた新たな試練──LCC台頭とコロナ禍が突きつけた「持続性の壁」──
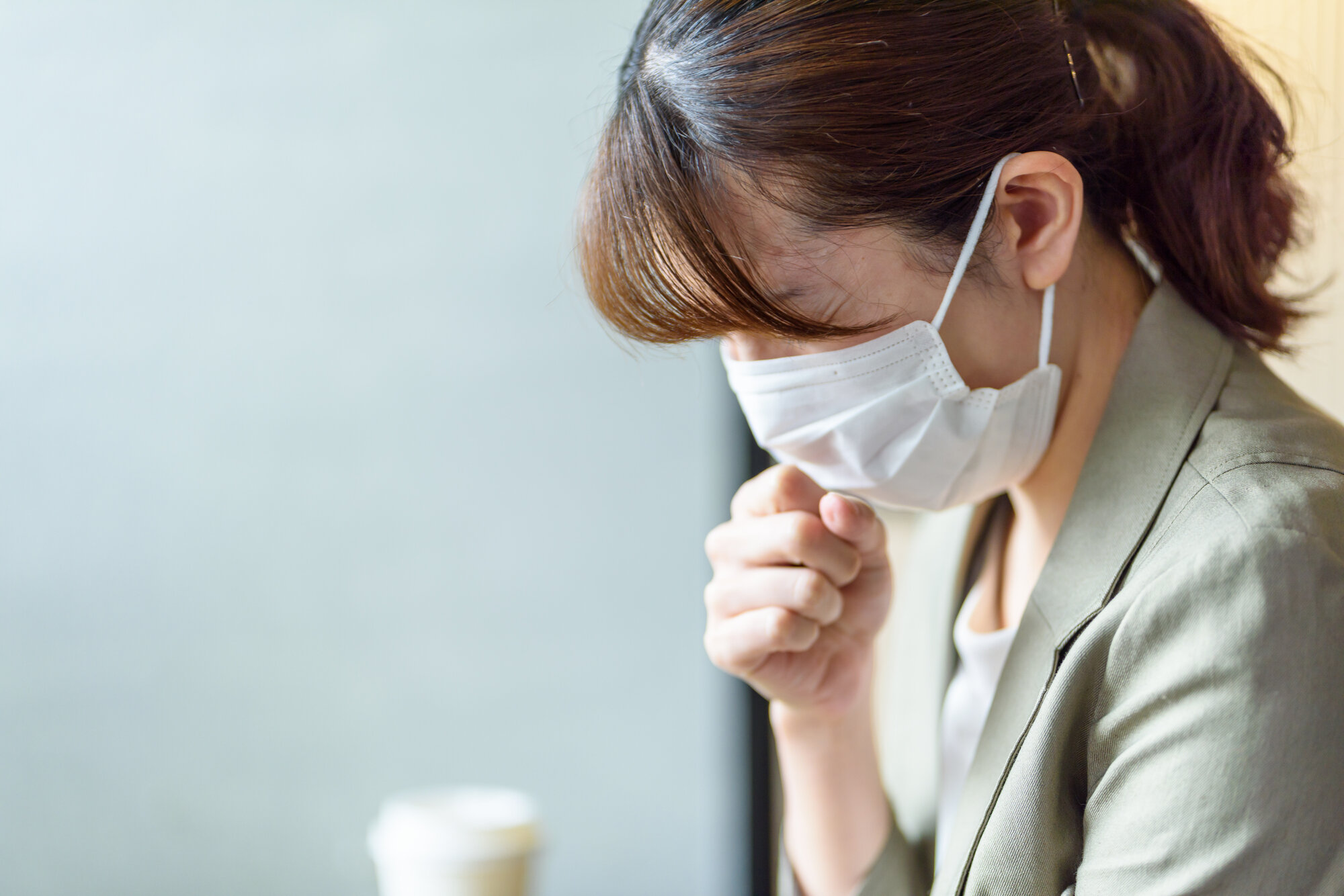
【第3回】再建後のJALに待ち受けた新たな試練
この記事を書いた人
目次
「奇跡の再建」の次にやってきたもの
ANAとの競争──国際線での明暗
LCC台頭がもたらした“価格の現実”
コロナ禍が突きつけた現実
それでも揺るがなかった「安全文化」
MBA的に見る“持続性の壁”
「奇跡の再建」の次にやってきたもの
2012年に再上場を果たした日本航空(JAL)は、営業利益率が世界トップ水準という“優等生企業”として再スタートを切りました。株価は堅調に推移し、再建の成功は国内外から高く評価されました。
しかし、再上場はゴールではなく、むしろ新たな試練の始まりでした。
ANAとのシェア争い
国内線市場では、ANAが着実にシェアを拡大。特に地方路線やビジネス需要の厚い都市間で優位に立ち、JALはシェア防衛に追われる構図が続きました。
LCCの台頭
ピーチ、ジェットスター・ジャパン、バニラエアなど、低コストキャリアが次々と市場参入。運賃水準は従来の半分以下になるケースもあり、価格競争に弱いJALの収益モデルを直撃しました。
パンデミックの衝撃
2020年のコロナ禍では、国際線旅客数が前年から96%減、国内線も70%減という未曾有の打撃を受けました。JALの営業収益は前年比65%減(2020年度:4,819億円)となり、再建後に積み上げてきた安定基盤は一気に揺らぎました。
つまり、「奇跡の再建」で得た称賛は、持続的な競争力を保証するものではなく、むしろ「次の成長モデルを描けるか?」という問いを突きつけるスタートラインに過ぎなかったのです。
ANAとの競争──国際線での明暗
再建後のJALは国際線拡大を成長の柱と位置づけました。しかし、実際にはANAとの競争で劣勢が目立つようになります。
国際線旅客数の差
2019年度の実績では、ANAの国際線旅客数が約1,050万人、JALは約860万人と約200万人の差がつきました。
羽田空港の発着枠
成長余地の大きい羽田空港国際線枠の割り当てで、ANAが有利なポジションを獲得。JALは後手に回り、成長の速度で差が開きました。
アライアンス戦略の差
ANAが加盟するスターアライアンスはユナイテッド航空やルフトハンザ航空を含む世界最大規模のネットワークを誇り、北米・欧州・アジアを結ぶ路線で強みを発揮しました。一方のJALはワンワールドに加盟していたものの、スケールで劣り、ネットワークの厚みでもANAに押されました。
結果として、国内線では価格競争にさらされ、国際線では規模拡張で遅れをとるという「板挟み」の状況に。再建後のJALが直面したのは、効率経営だけでは乗り越えられない、構造的な競争の壁でした。
LCC台頭がもたらした“価格の現実”
2010年代に入ると、国内外でLCC(格安航空会社)が急成長しました。
・ピーチ(ANAグループ)、ジェットスター・ジャパン、バニラエアなどが国内線に参入
・運賃は大手航空会社の3分の1程度に設定され、価格競争が加速
・アジアでもエアアジアやスクートなどが台頭し、国際線でも低価格の選択肢が急増
JALも「ZIPAIR Tokyo」を設立(2018年)し、LCC市場に参入しましたが、ANAに先行される形となり、LCC戦略では出遅れ感が否めませんでした。
費用は留学の1/10
AACSB認証の高品質な米国MBAをオンラインで取得
まずは無料の説明会にご参加ください。
コロナ禍が突きつけた現実
2020年、新型コロナウイルスのパンデミックは航空業界全体に壊滅的な打撃を与えました。
・2020年度、JALの旅客数は前年比76%減
・売上高は約4,815億円(前年比65%減)、最終赤字は約2,868億円
・2012年の再上場後、初の赤字転落
一方で、固定費比率が高い航空産業では需要減少が直撃し、再建で築いた高利益体質も一瞬で崩れました。
「筋肉質になったはずのJALが、なぜ再び脆さを見せたのか?」──答えは、外部ショックに耐えうる新たな事業ポートフォリオを持っていなかったことにあります。
それでも揺るがなかった「安全文化」
コロナ禍で多くの便が運休する中でも、JALは「安全と品質」を維持する姿勢を貫きました
。・マスクや消毒を徹底し、世界で初めて「COVID-19 安全評価 5スター」をSkytraxから認定
・客室乗務員や整備士の再教育を継続し、運航再開後に即対応できる体制を確保
この点は、再建時に培われた「現場に責任を戻す」文化が生きていた証でもあります。
MBA的に見る“持続性の壁”
JALが直面した課題は、MBAの視点で整理すると以下の通りです。
| MBAの論点 | JAL事例の示唆 |
|---|---|
| 競争戦略論 | LCC台頭への対応は「価格」か「差別化」かを明確にせねばならない |
| アライアンス戦略 | ANAとの国際線シェア争いで見えた“規模の経済”の限界 |
| リスクマネジメント | コロナ禍のような外部ショックに備える事業ポートフォリオ設計の重要性 |
| 組織文化論 | 危機下でも揺るがなかった「安全最優先」の文化の強み |
再建は成功したものの、その後の競争環境に対応する新たな構造改革は十分ではなかったことが浮き彫りになりました。
次回予告
第4回では、「JALの未来」に焦点を当てます。GX(グリーントランスフォーメーション)、新たな需要の創出、観光立国との連動──持続可能な航空会社へと進化できるのか。そこから読み取れる、私たちビジネスパーソンへの教訓を整理します。
次の記事はこちら
費用は留学の1/10
AACSB認証の高品質な米国MBAをオンラインで取得
まずは無料の説明会にご参加ください。
アビタスでは、国際認証を取得している「マサチューセッツ州立大学(UMass)MBAプログラム」を提供
国際資格の専門校であるアビタス(東京)が提供しているプログラムで、日本の自宅からオンラインで米国MBA学位を取得できます。
日本語で実施する基礎課程と英語で行うディスカッション主体の上級課程の2段階でカリキュラムが組まれているため、英語力の向上も見込めます。
世界でわずか5%のビジネススクールにしか与えられていないAACSB国際認証を受けており、高い教育品質が保証されているプログラムです。
自宅にいながら学位が取得できるため、仕事や家事と両立できる点も強みです。
アビタスでは無料のオンライン説明会と体験講義を実施しています。興味のある人はお気軽にお問い合わせください。
 UMass MBA
UMass MBA