本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。
- 2022/09/27公開
- 2022/10/03更新
頼れるエースは内部監査人

みなさん、こんにちは、アビタス講師の八野です。このコラムは、いつもの教室から飛び出して、実務で遭遇したあれやこれやについて、驚いたこと、感心したこと、考え込んでしまったことなどを本音トークでお伝えいたします。
第2回は、「頼れるエースは内部監査人」についてお話します。
目次
1.不正の専門家はいない
2.国際化の嵐
3.じゃあ、こうする!
1.不正の専門家はいない
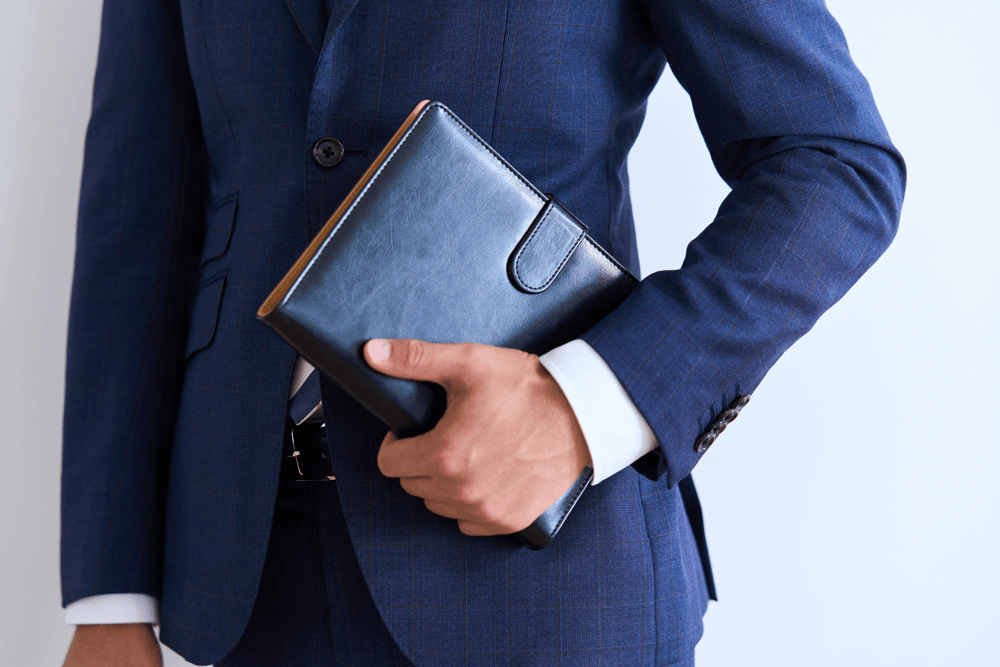
前回は、「企業内部に不正の専門家はいない」という「衝撃の事実」について、お話ししました。(前回のコラムはこちら)内部や外部の監査人は、その目的が違うため、不正の兆候(Red Flag)に気付くことはできても、不正事案そのものを扱う(例えば、調査の一環で証拠を保全するなど)ことはできない、いわんや、素人の総務部長などが不正事案を担当することは、調査手法としても、法的にも大変危険なことをしている、というお話でした。
その一方企業実務の現場では、警察や弁護士に相談するほどでもないが、きちんと不正調査をしたい(しなければいけない)というニーズがあることもお話ししました。
つまり、需要があるのに供給できない状態が、日本企業の実態です。
じゃあ、どうする?
2.国際化の嵐
世は押しなべて国際化の流れです。私が若かりし頃は、海外子会社があるという企業は、それなりに大きな会社ばかりでしたが今や、普通の会社が普通に持っています。特に最近は、世界的なサプライ・チェーン網が発達し益々、海外子会社は重要な役割を担うようになってきました。
例えば、東南アジアで水害が起こると、仕事帰りのコンビニで、ある製品が品薄になっていたりして、生活上実感することもあるでしょう。その様なビジネス環境において、もし海外子会社で不正があった場合、日本の本社からは誰が現地調査に乗り込みますか?
実は、海外子会社における不正は結構多く発生しています。本社の管理が行き届かなかったり、日本からの駐在員が現地の悪い社員に言いくるめられたり、原因は色々あります。要は、日本に事務所を持つことと比べて、不正リスクは非常に高いということです。
また国際化の波は、何もカタギの仕事だけには限りません。犯罪もドンドン国際化しています。
マネーロンダリングやサイバーアタックなどは国際化の最たる例で、いつ自社が巻き込まれるかわかったものではないのです。
例えば、電子メールに添付されていたインヴォイスを開封すると会社のメイン・サーバーがダウンして大騒ぎになっていたりして、生活上実感することもあるでしょう。
それでなくても不正リスクが高い海外子会社を、世界的犯罪者組織が虎視眈々と狙っています。
じゃあ、どうする?
3.じゃあ、こうする!
現場で、じゃあ、どうしたらいいですか?不正事案を担当できる人材は獲得できますか?と、ご相談を受けた際にお勧めしている方法があります。
それは、「内部監査人に公認不正検査士(CFE)の資格を取得させる」やりかたです。内部監査人が、公認内部監査人(CIA)の資格を取得済みであれば、なお良し、です。
まず、内部監査人は企業ガバナンスを実現するために、リスク・マネジメントに対応した内部統制などの妥当性、有効性を監査しています。リスク・マネジメントの中には当然、不正リスクも含まれますので、内部監査人は既に、不正を予防することや、発見することについて一定の知見、経験を積んでいます。
内部監査のご経験がある方は身に染みてお感じになられていると思いますが、この「一定の知見と経験」は、なかなか一筋縄では会得できないもので、大変貴重な能力であると思います。
その上で、不正に関するお勉強と実務をこなして実力をつければ、不正の予防から、発見、不正調査までを「一気通貫」でこなすことができる(すごい)人になります。
私の知る限り、今の日本企業ではごく少数です。
また更に、国際化の環境を考えると、国際的な基準などをもとに資格を付与しているCIAやCFEの取得をおすすめしています。
例えば、不正調査においては、「裁判になることを常に意識して手続きを行う」のですが、国・地域によって法体系や裁判の形式、手続きなどに違いがあり、このあたりの国際的な知識がないと対応できないことになります。
米国の法廷ドラマで、主人公の弁護士が陪審員に向かって大逆転の証拠を示して、勝利を勝ち取ったりしていますが、あんなの日本ではあり得ません。法体系や裁判のやり方が違うのです。
という訳で、内部監査人(CIAホルダーが良い)が、きちんとした不正検査の勉強と実務をする(CFEの資格を取る)ことにより、日本の企業社会では稀有の人材が誕生します。
取締役や経営者、ひいては株主の立場から考えると、これほどの「頼れるエース」は居ないのではないでしょうか。
みなさんもオオタニサンに負けず、二刀流を目指してみてはいかがでしょうか。
CFEについてもっと知りたい方はこちら
監修
八野 寿典
アビタスUSCPA(米国公認会計士)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)各プログラム講師
 CFE
CFE






