本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。
合格者の声
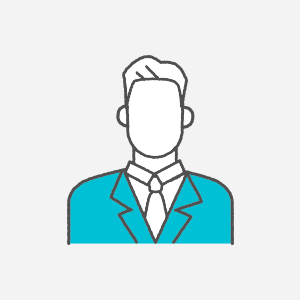
専門知識についても、疎かったIT統制や、業務処理統制の考え方も身につき、今後の業務に生かせそうだと確信しています。
- 匿名希望さん
-
某食品メーカー内部監査部課長
学習期間:1年
卒業時役職:某食品メーカー内部監査部課長
- 通信
- 40歳代
- 国内_通学圏
- 監査経験有
- 製造業
- 専門知識を身につける
- CIA 合格時期 ・ 受験回数
-
- PART1 / 2022年1月 / 1回
- PART2 / 2022年3月 / 1回
- PART3 / 2022年5月 / 1回
CIAを目指した理由
私は某食品メーカーグループの子会社で経理をしていましたが、親
子会社時代から、親会社の内部統制監査を受け、また子会社でも金
私はどちらかというと、最初に知識を体系立てて学ぶことが性に合
アビタスを選んだ理由・メリット
CIAについての合格実績が高かったこと、オンラインでのセミナ
CIAの学習を通じて得た事、メリット等
現在の勤務先(執行役員制度を採用)の内部監査部は、もちろん経
これからCIAを目指す方へのアドバイス等
CIA試験は、他の試験と同様、専門的で覚えるべきことが多い試
かといって丸暗記というよりは考え方を身につけることが大事な試
ただ、その考え方はテキストの読み込み以上に、実際にMC問題な
また、これは市販の勉強法にもあったのですが、インプットした知
なお、CIAの勉強に、勤務先の考え方を持ち込まない(その企業
最後に、オンライン質問教室を拝見すると、非常に細かい論点を深
 CIA
CIA