本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。
IFRS実務者インタビュー
【vol.11】実務と転職を支えたIFRS検定の確かな効力。
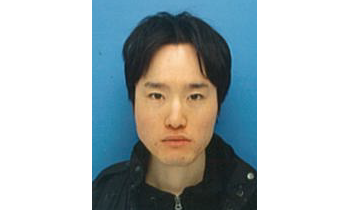
鳴田 浩士さん
外資系企業 経理財務、FP&A
- 経理財務経験:有
- 英文経理財務経験:有
- システム経験:有
- TOEIC:725点
- 日商簿記:2級
実務と転職を支えたIFRS検定の確かな効力。
外資系企業を中心に、経理財務およびFP&Aの実務経験を積んできた鳴田さん。
USCPAや簿記1級の学習を進めるなかで、育児との両立を考慮し、限られた時間でも取得できるIFRS検定の学習を決意。
現職はIFRS採用企業で実務経験は豊富であったものの、「客観的な証明」としてのIFRS取得は転職活動において大きな武器になったと語ります。さらに、収益認識・リース・研究開発費といった論点について、実務に即した形で知識を活用しており、IFRS検定の学習が日常業務の品質にも影響を与えていると実感しているとのこと。
USCPAとのつながりや、IFRSが実務とキャリアにどう生きるのかを、自身の体験を通して語っていただきました。
記事内容はインタビュー当時のもので現在は異なる場合があります。予めご了承ください。
ー経歴についてお聞かせください。
新卒で日系企業に入社しました。それ以降は外資系企業にて経理財務やFP&A業務に従事しています。勤務先は主にIFRS採用企業です。
ーIFRSに出会ったきっかけは何ですか?
IFRS採用企業での業務においてGL担当となり、収益認識基準反映やリース会計を扱うようになったためです。IFRS検定に出会ったきっかけは転職活動において、客観的にIFRS習熟の証明できるものを探していたときです。
ー他に取得を目指されている資格はありますか?
USCPAと簿記1級です。USCPA学習はIFRS検定学習より前から取り組んでいましたが、家族ができたことでまとまった勉強時間を確保するのが難しくなりました。そこで、細切れの学習時間でUSCPAに取り組み続けるよりは、比較的確度が高そうで、半年あれば取得できると思われたIFRS検定取得を優先することにしました。
ーUSCPA取得を考えたきっかけは何ですか?
当時働いていた会社の上司がUSCPA取得者だったことがきっかけです。それに加え第一に会計原則を知っていることが不可欠である経理財務分野では、勉強が必要不可欠だと感じていました。USCPAを取得できれば、アカウンティング関連分野を網羅・習熟している証明になりますし、実際に外資系企業でも活躍できると考えた次第です。
ーアビタスのIFRS検定講座を選んだ理由は何ですか?
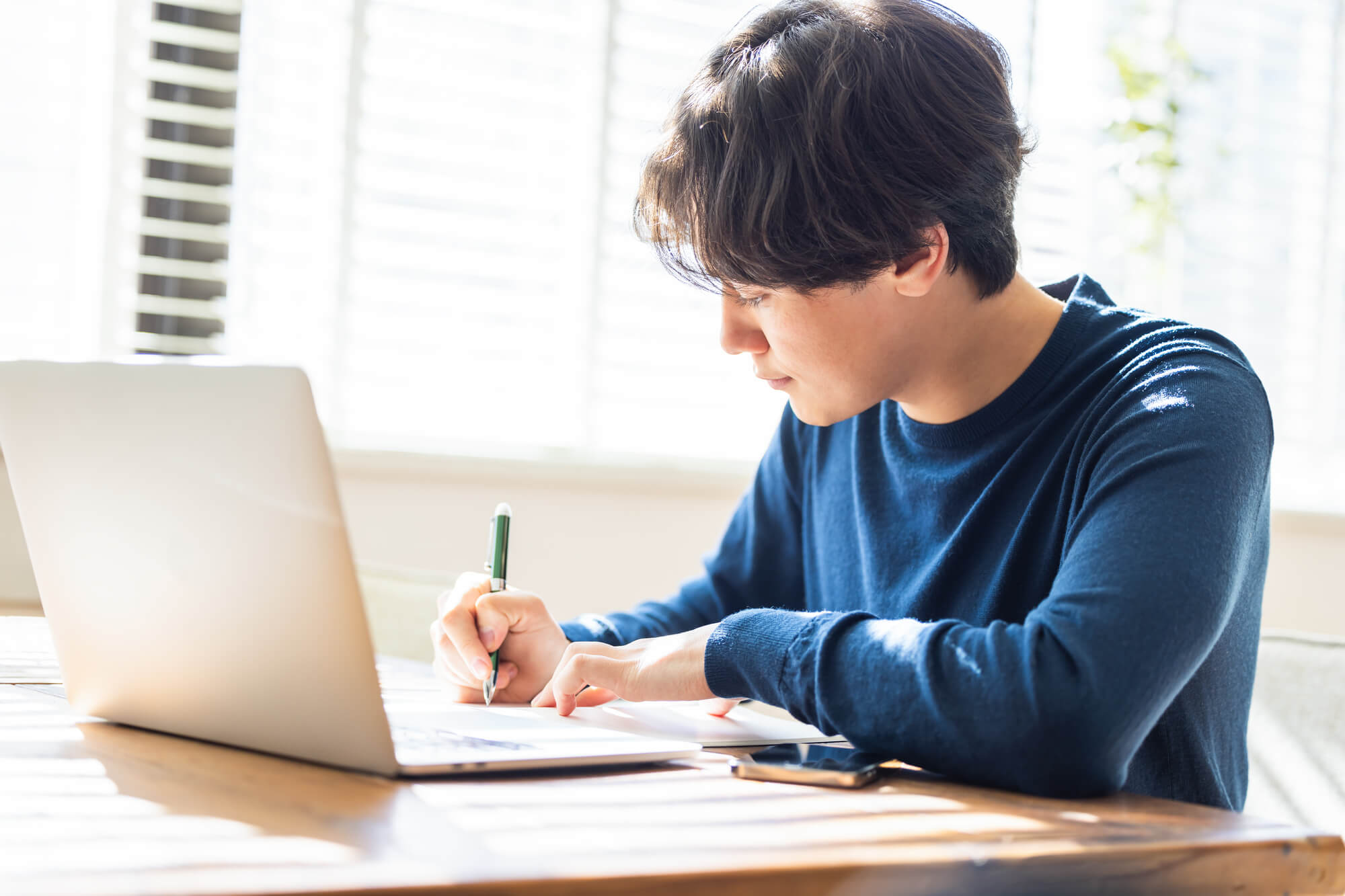
ーIFRS検定取得の難易度についてどうお考えですか?
適切な難易度だと思われます。全く経理経験がない、あるいは簿記3級程度の知識の方でも、IFRS検定は無理なく取得可能だと思います。もちろん事前に知識や経験がある方よりはハードルが高くなると思いますが、半年程度の学習期間で合格可能だと思われます。
ーUSCPAとIFRSの内容のつながりについて、どう思われますか?
USCPAのFAR学習がIFRS検定取得に大いに役立ちました。FARは主要な会計原則を網羅的に学ぶことができるからです。GAAPは違えども共通・類似する点は多々ありますため、そのつながりを感じながら学ぶことができたと思います。IFRS検定に取り組んでからCPA学習に取り組むことも、基礎を作る意味で有効かもしれません。
ーIFRS検定を取得されて、変わった実感はありますか?
はい、転職活動においても役立った実感はあります。上場企業やその関係会社での面接を通して、IFRS検定の認知度を感じました。面接でもIFRSの実務経験があり、かつ検定にも合格していることは自己PRとなりました。実務経験を話すにしても、資格によって裏付けされた自信がもてますし、実際にその会社で行われているであろう会計処理についても言及できることが強みになったと感じます。
ー実務において、IFRS検定はどう生きていますか?
実務に生きている点を3点紹介させていただきます。
第一にIFRS自体を網羅的に学習することは、取引の会計処理を議論する機会において検討すべき点の抜け漏れを防いでくれます。収益認識基準の5つのステップを例に挙げますと、新しい商取引での売上計上をするにあたり、契約上の履行義務は何か?価格をどう配分するか?というような論点をおさえたうえで議論に参加できることで、網羅的に当該取引の会計処理方法を検討できます。
次にリース取引の会計処理決定にも役立っています。JGAAPで処理したリース取引をIFRSへ変換するGAAP調整や、昨今の新リース会計基準導入における論点理解がスムーズに行えます。使用権資産の測定や、そもそものリース種類判定フローを経理部内外へ説明できることは一定の信頼に繋がります。
最後に、製造業におけるR&D(Research and Development)費用のGAAP差理解も役立ちました。製造業以外の方には馴染みがないかもしれませんが、IFRSで財務諸表を作るときにJGAAPとの間でGAAP差が大きい代表例です。R&D費用は、IFRSでは商品化の実現可能性が高く、納品先が決まっているような状態であれば資産計上ができるのですが、日本会計基準の場合はすべて費用計上されてしまいます。現在所属している会社は、IFRSで財務諸表を作り、税務申告でJGAAPへ変換する手続きをとっていますが、このGAAP差でかなり大きなP&L impactが発生してしまいます。このGAAPの違いに言及して説明できることは、マネジメント層や金融機関からの一定の信頼につながると思われます。
 IFRS
IFRS